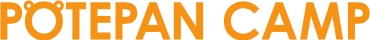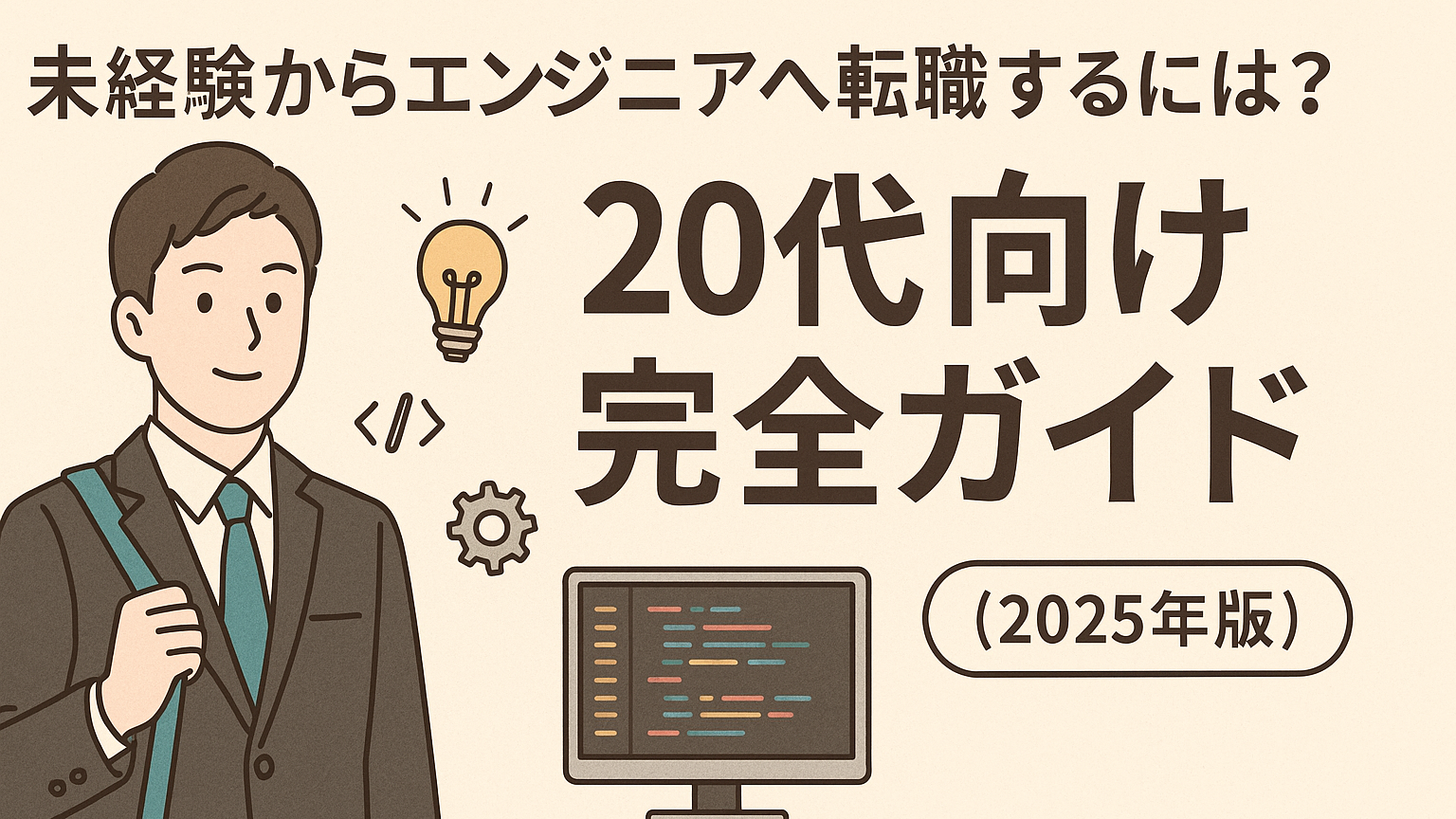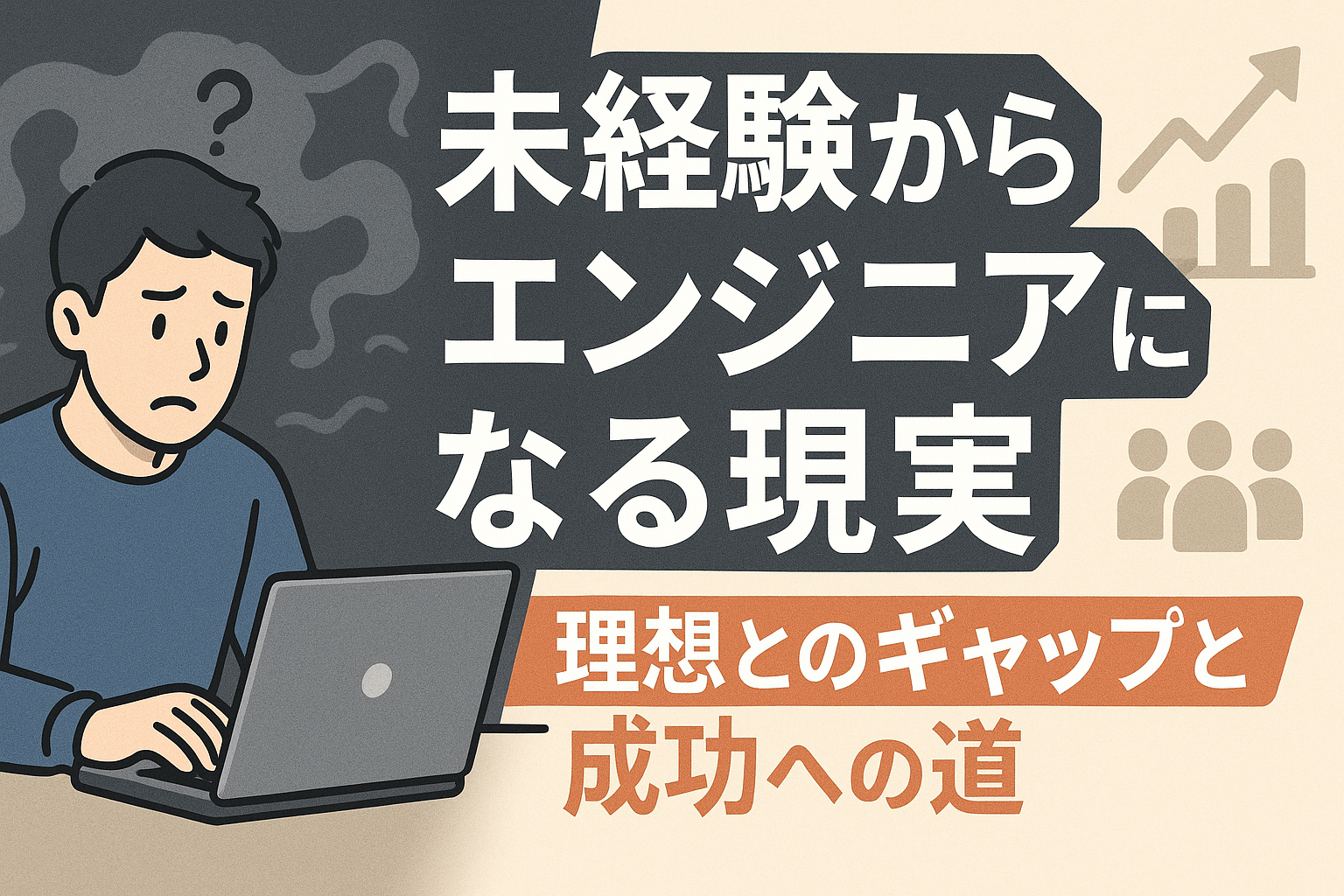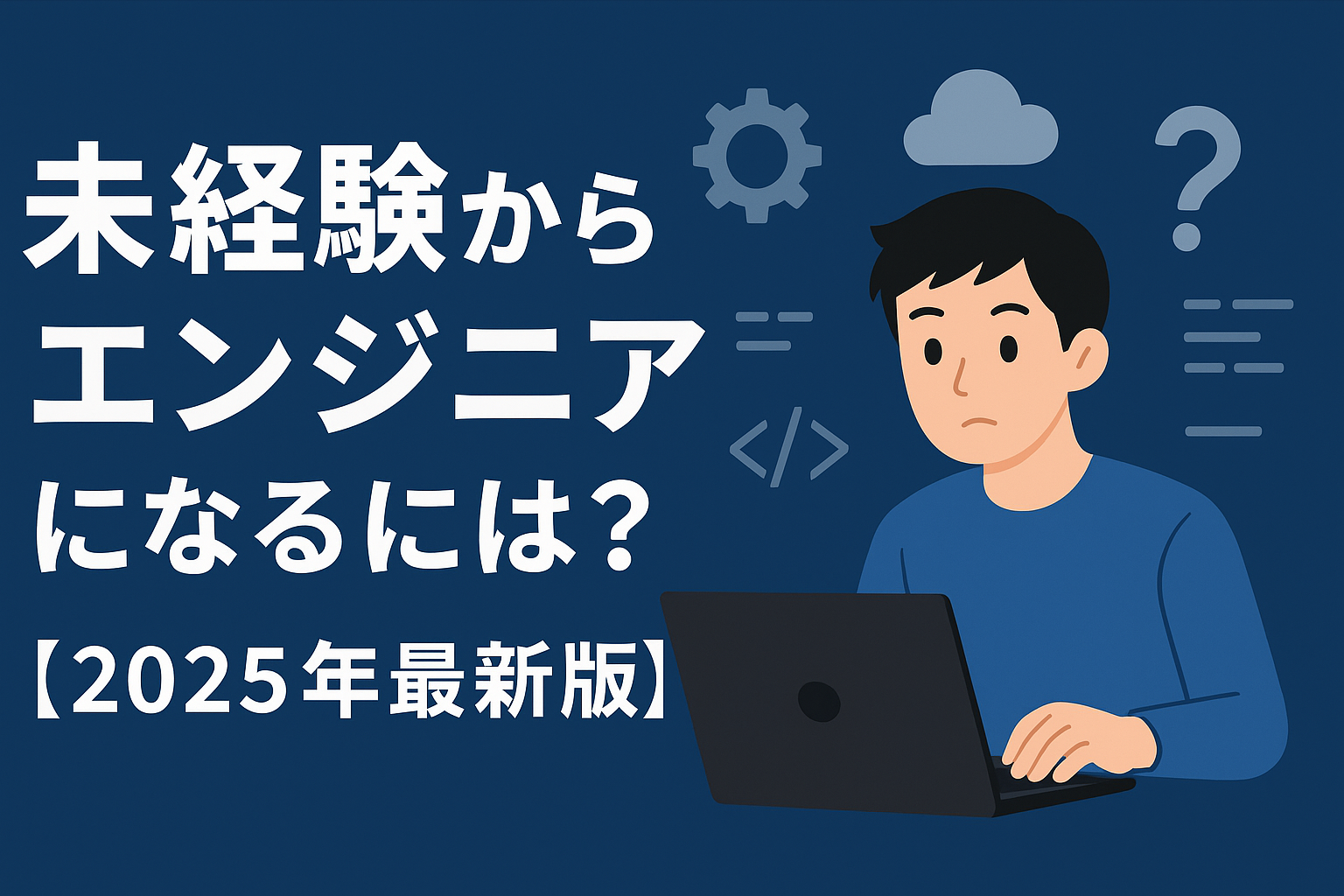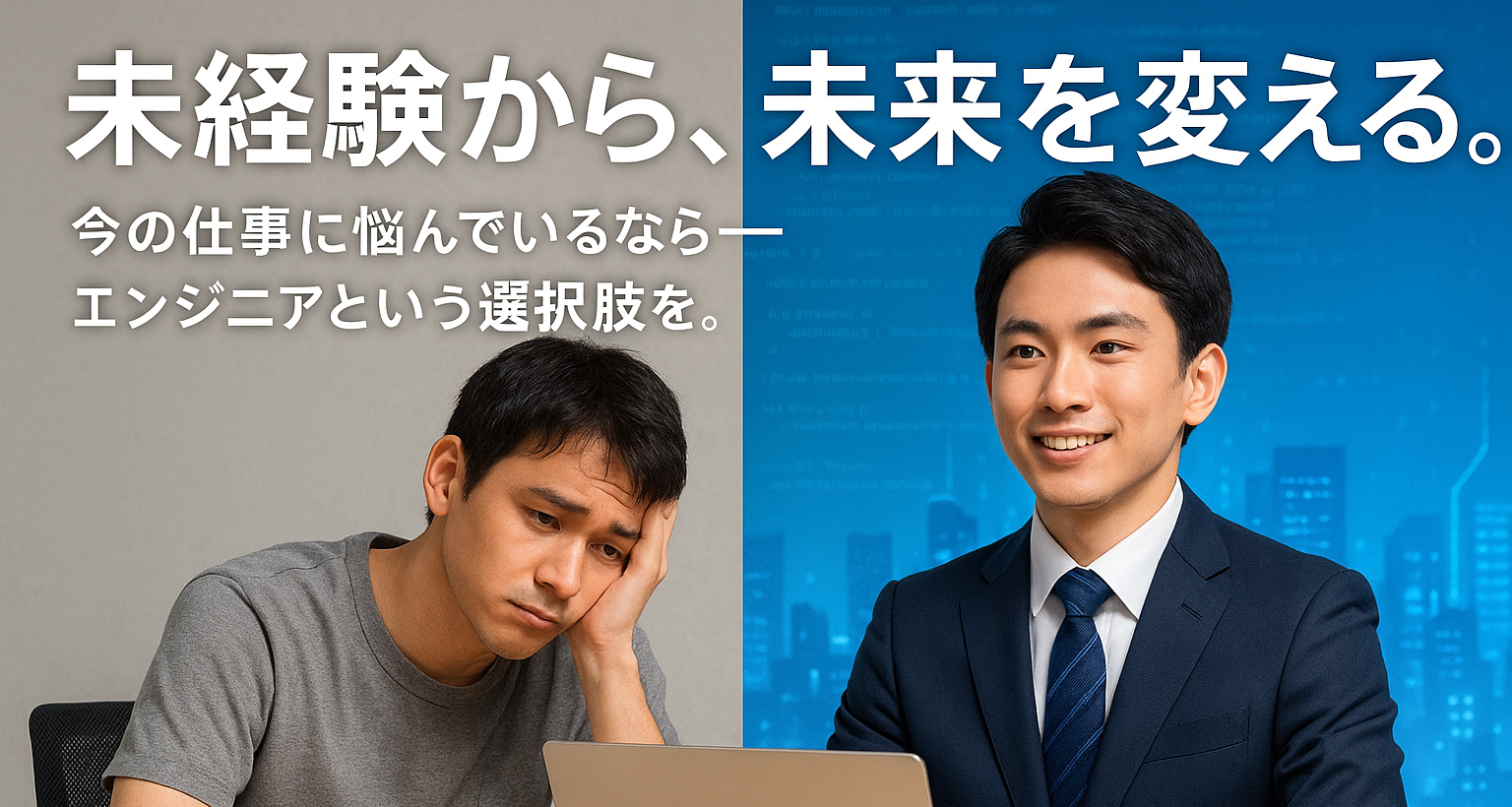未経験エンジニア必見!ポートフォリオサイトデザインの基本と成功の秘訣

SPEAKER

株式会社ポテパン代表取締役社長|宮﨑大地
IT教育事業「ポテパンキャンプ」代表。未経験からエンジニアを目指す若者の支援に特化したプログラミングスクールを運営し、これまでに数千人以上のキャリア転換を成功に導く。現場で求められる実践力にこだわり、受講生一人ひとりの成長を後押しする教育設計と、確かな就職支援が高く評価されている。現在もキャリアアドバイザーと企業の採用支援を行っており、エンジニアと現場の橋渡し役として活動中。
未経験エンジニアの皆さん、ポートフォリオ作りに悩んでいませんか?「ポートフォリオって何?本当に必要なの?」と疑問に思うこともありますよね。筆者も初心者だった頃は同じ不安を抱えていました。でも安心してください。エンジニアのポートフォリオは就職・転職活動で大きな武器になります。本記事では、初心者にも分かりやすく エンジニア ポートフォリオ デザインの基本やコツ、そして実例までカジュアルに解説します。読み終える頃には、きっと「あ、自分も作れそう!」と思えるはずです。それでは始めましょう 🎉
ポートフォリオとは?なぜエンジニアに必要なのか

まずポートフォリオとは何かを押さえましょう。ポートフォリオとは 「自分が作ったもの(成果物)をまとめたもの」 です。もともとは芸術分野で使われていた言葉ですが、エンジニア業界でも自作したサービスやプロダクトの集大成という意味で使われます。要するに、自分の実力や成長を示す作品集だと思ってください。
では、なぜポートフォリオが必要なのでしょうか?理由は大きく分けて2つあります。
① ライバルと差別化するため
近年、プログラミング学習の普及やIT業界への転職ブームもあり、エンジニア志望者が急増しています。インターンでさえ競争が激しく、同じ未経験ならポートフォリオがあるかどうかで大きな差がつく時代になりました。実際に「未経験OK」と言っても応募者が多く、企業は少しでも実力が見える人を選びたいもの。ポートフォリオがあれば自分の強みをアピールして他の候補者と差別化できるわけです。
② スキルを証明するため
新人エンジニアの採用では、「本当にこの人やれるかな?」という企業側の不安があります。特に実務未経験者を育成するには企業にコストがかかるため、書類選考の段階でポートフォリオから実力を判断しようとする企業も多いのです。履歴書や経歴書だけでは皆フォーマットが同じで、なかなか差がつきませんし、面接で「プログラミング得意です!」と言葉で言っても信用度はイマイチですよね。しかしポートフォリオがあれば「こんな作品を作りました!」と実物で技術力を示せるので、言葉より説得力が増します。実際、履歴書+ポートフォリオという形で提出すると採用担当者の目に留まりやすく、内容もしっかり見てもらえる可能性が上がるんです。
要するに、ポートフォリオはあなたの実力と熱意を可視化する名刺代わり。作る過程で自分のスキル整理にもなりますし、完成したポートフォリオは企業に「自分はこんなことができます!」と胸を張って示せる武器になります。初心者のうちは手探りで大変かもしれませんが、だからこそ小さなものでもいいので自分の作品を形にしてみることが大切ですよ💪
採用担当の心を掴む!見やすいポートフォリオデザインの基本原則

ポートフォリオを作る目的が分かったところで、次はデザインの基本原則です。ここで言う「デザイン」とは、見た目の美しさだけでなく情報の整理術も含みます。「せっかく作ったのに採用担当者にちゃんと見てもらえなかった…😭」なんてことにならないよう、見やすく・目に留まりやすいポートフォリオにするコツを押さえましょう。
ポイントは大きく分けて以下の通りです。
1.ひと目で内容が分かる構成にする
ポートフォリオは最初の数秒の印象が勝負です。採用担当者はたくさんの候補者を見るので、パッと見て重要な情報が伝わるレイアウトにしましょう。にもある通り、「自己紹介(プロフィール)」「スキルレベル」「将来のビジョン」「作品紹介」「仕事への姿勢」など盛り込みたい要素は5つありますが、フォーマットは自由です。これらを見出しやセクションに分けて整理し、一目で全体像が掴めるように配置すると良いでしょう。「まずプロフィールとスキル概要があって、その後に主な制作物が並んでいるな」くらいスッと理解できる構成が理想です。
2.必要な情報を漏れなく入れる
ポートフォリオには最低限入れておきたい情報があります。例として採用エージェントの提案する項目を参考にすると、以下のようなものが挙げられます:
・自己紹介:簡単な経歴や得意分野、エンジニアを目指した動機など
・スキルセット:使用できる言語やフレームワーク、スキルレベル(※初心者なら習得中の技術も書いてOK)
・制作物・プロジェクト一覧:過去に作ったアプリやサイトの概要(役割や使用技術も添える)
・リンク集(成果物のURLやGitHub、SNSなど):ソースコードやデモにアクセスできるように
・今後の目標:学びたい技術や挑戦したい分野など将来のビジョン
作品を箇条書きで並べるだけでは意図が伝わらず印象に残りにくいので、各作品ごとに「何を作ったか」「工夫した点」「得られた知見」なども簡潔に添えるとなお良いです。あなたの人柄や開発への姿勢も伝わりますし、「この人は将来○○をやりたいのか」とイメージしてもらえると面接でも話が弾みます。
3.読みやすいデザインにする
情報を詰め込むだけでは相手に伝わりません。デザイン面でも読みやすさに配慮しましょう。具体的には、適度な余白を取りシンプルなレイアウトにする、見出しや強調したいテキストはサイズや色にメリハリをつける、フォントは読みやすいものを選ぶ等が基本です。デザインの専門用語で言えば「近接」「整列」「強弱(コントラスト)」「反復」といった原則を意識するのがコツ。例えば関連する情報はグルーピングして近くに配置し、全体の整列を揃えて乱雑に見えないようにします。強調したいポイントは太字や色で目立たせますが、強弱をつけすぎるとチカチカするのでバランス良く。デザインに自信がなくても、この基本原則を押さえれば「なんか見づらい…」という事態は避けられるでしょう。
4.統一感とオリジナリティ
ポートフォリオ全体のトーン&マナー(色使いやフォント、デザインパターンなど)は統一しましょう。統一感があるとプロっぽく見え、信頼感も上がります。ただし、画一的すぎると埋もれてしまうので自分らしさも少し表現したいところ。色は自分の好きなカラーや印象づけたいイメージカラーを使ったり、ロゴやキャッチフレーズでオリジナル感を出したりするのもアリです。派手すぎず地味すぎず、あなたの個性が垣間見えるデザインを目指しましょう。それが採用担当者の記憶に残るポイントにもなります。
以上の基本を踏まえてデザインすれば、見やすさと内容の充実したポートフォリオになります。ポイントは「相手目線で考える」こと。「自分だったら初見で何が知りたいか?」と意識しながら作ると、大きくズレることはないですよ😉
ポートフォリオ作成に役立つAIツール活用術(Stitch・Claude・ChatGPT)

「よし、作るぞ!」と思っても、いきなりゼロからポートフォリオを作るのは大変ですよね。ここで心強い味方になるのがAIツールです。最近はエンジニア向けにポートフォリオ作成を手助けしてくれるAIツールも充実しています。この章ではおすすめのツール GoogleのAI UIデザインツール「Stitch」, Anthropic社の「Claude」, OpenAIの「ChatGPT」 の3つをご紹介し、それぞれどのように活用できるか簡単に説明します。
Google Stitch – UIデザインをAIで爆速生成!
2025年のGoogle I/Oで発表された注目ツールが Google Stitch です。これはテキストで書いた指示や参考画像を入力すると、あっという間にUIデザインとフロントエンドのコードを生成してくれるという画期的な実験的ツールです。例えば「シンプルで青を基調としたポートフォリオサイトのデザインが欲しい」と英語で指示すると、わずか数分でそれに沿った複数パターンの画面デザイン案を作ってくれるんです。
Stitchの使い方はシンプル。Google Labs上で提供されており、まずテーマや雰囲気(例えば「クリーンなモダンデザイン」など)を選び、自然言語でレイアウトや要素の希望を入力します。さらに参考にしたい画像や手描きのワイヤーフレームがあればアップロードして補足できます。するとAIがあなたの指定に合わせて複雑なUIデザインとHTML/CSS/JavaScriptコードを自動生成!あとはそれをエクスポートして、自分のポートフォリオとして微調整すればOK。コーディング未経験でもプロっぽいデザインを作れるので、デザイン面で悩んで手が止まっている方には救世主的なツールです。
Stitch活用のポイント: 便利だからといって丸投げすると自分らしさが無くなってしまいます。生成後のデザインは「自分だったらもう少しここをこうしたい」という部分をしっかり編集して、あくまで自分のポートフォリオとしてブラッシュアップすることが大事です。AIの叩き台+自分のアレンジで、効率良く魅力的なUIを作りましょう。
Claude – 大容量コンテンツもおまかせ!文章&コードアシスタント
次に紹介する Claude(クロード) は、ChatGPTのライバルとも言われる高度な対話型AIです。Anthropic社が開発したこのモデルの強みは、なんといっても超大量のテキストを一度に読み込めること。通常のChatGPTが数千〜数万文字の入力しか扱えないのに対し、Claudeは最大10万トークン(約7.5万単語!)もの文書を一度に処理できます。つまり、長大なドキュメントやコードベースを丸ごと読み込ませて要約や分析をしてもらうことが可能なのです。
ポートフォリオ作りでClaudeが活躍する場面としては、例えば以下のようなケースがあります:
・長い文章の要約
自分の経歴やプロジェクトの詳細を書き出したら長文になってしまった…というとき、Claudeに「これを初心者にも分かるように3行でまとめて」とお願いすればスッキリ要約してくれます。伝えたいポイントを抽出してくれるので、ポートフォリオの説明文が簡潔で読みやすくなります。
・コードの解説やドキュメント生成
ポートフォリオに載せるプロジェクトのソースコードに、コメントや説明を付けたいときもClaudeが便利です。プロジェクト全体のコードを(秘密情報に注意しつつ)入力して「このコードの概要と特徴を説明して」と尋ねれば、まとまりのある解説を生成してくれます。膨大なコードでも一度に理解してくれるので、「部分部分説明したけど全体像の説明が難しい…」というときに助かります。
・文章のブラッシュアップ
ChatGPTと同様に、Claudeも文章の校正やリライトが得意です。自分で書いた自己PR文を投入して「もう少しカジュアルな口調にして」とか「熱意が伝わる表現に変えて」と指示すれば、グッと魅力的な文章に直してくれるでしょう。特にClaudeは指示に対する素直さや安定感に定評があるので、長めの説明文の推敲などで活用できます。
要は、Claudeは大量の情報を扱いつつ文章やコードを整えてくれる相棒です。ChatGPTと比べると知名度は低いですが、「裏方の優秀な編集者」的ポジションでポートフォリオ制作を支えてくれるでしょう。
ChatGPT – アイデア出しからコーディングまで頼れる万能AI
最後はお馴染み ChatGPT。既に触ったことがある方も多いと思いますが、ポートフォリオ作成にも幅広く使える万能ツールです。使い方次第では「相棒」というより**「先生」や「ペアプロの先輩」**のような心強さを発揮してくれます。特に初心者エンジニアにとってありがたい活用法をいくつか紹介します。
構成や内容の相談相手に
「ポートフォリオに何を書けばいいか分からない…」となったら、まずChatGPTに相談してみましょう。「エンジニア志望のポートフォリオにはどんな項目を入れるべき?」と聞くと、自己紹介・スキル・プロジェクト・連絡先…と必要事項をリストアップして教えてくれます。頭の中が整理されていない段階でも、対話しながらアイデアを引き出してくれるので、企画のブレスト相手として優秀です。
文章作成をサポート
ChatGPTは自然な文章の生成が得意なので、自己紹介文や各プロジェクトの説明文を書く際にも役立ちます。「未経験から独学でWeb開発を学びました。情熱をアピールできる自己紹介文を考えて」とお願いすれば、気の利いた自己PR文の草案を作ってくれるでしょう。ただし、そのままコピペではなく自分の言葉で手直しするのを忘れずに! AIの文章は便利ですが、みんなが使うと似たような表現になりがちなので、最後は自分らしさを加えることが大切です。
コーディングやサイト構築の助っ人に: 「HTML/CSSでポートフォリオサイトを作りたいけど、コードを書くのが不安…」という人もChatGPTに頼ってみましょう。実は簡単な指示を出すだけでWebサイトの雛形コードを生成してくれるんです。ある初心者の方は、ChatGPTに「自分用のWebサイト作りたい」と伝えただけで、index.html、about.html、works.htmlといったファイル構成から中身のコードまで提案してもらえたそうです。例えば以下のようにフォルダとファイルのひな型が返ってきました:
perl
コピーする編集する
my-portfolio-website/
├─ index.html (トップページ)
├─ about.html (自己紹介ページ)
└─ works.html (制作物一覧ページ)
ChatGPTはプログラミングの質問にも答えてくれるので、「レスポンシブ対応するにはどう書けばいい?」「フォームの送信部分のJavaScriptを書いて」といった具体的なお願いも可能です。エラーが出たらエラーメッセージを伝えて解決策を聞くこともできます。まさに24時間頼れるメンターですね。のようにChatGPTを使ったWebサイト制作の方法を解説する記事も増えており、アイデア次第でどこまでも活用できる万能さがあります。
ChatGPT活用のポイント: 困ったときはまず聞いてみる姿勢が大事ですが、丸投げしすぎないことも重要です。提案されたコードを理解し、自分なりにカスタマイズすることで実力も付きます。ChatGPTは便利な補助輪ですが、最終的にハンドルを握るのは自分という意識で使いましょう。
以上、3つのAIツールを紹介しましたが、目的に応じて使い分けるのがおすすめです。デザイン面はStitch、文章や要約はClaude、総合力ではChatGPTというように、得意分野で手を借りれば作業効率が格段にアップします。「AIに頼るなんてズルい?」なんて思う必要はありません。今やプロも使っているツールですし、大事なのは完成物のクオリティと自分の成長です。AIを上手に使って、あなただけのポートフォリオを作り上げましょう!
成功するポートフォリオの具体例&デザインの工夫
百聞は一見に如かず。ここでは実際に成功につながったポートフォリオの例や、ユニークなデザインの工夫をいくつかご紹介します。先人たちの作品を見ると、「こんな表現もアリなんだ!」と刺激になりますよ。自分の制作の参考に、良いところはどんどん真似しちゃいましょう。
シンプルでも中身充実!Hodaさんのポートフォリオ
とあるエンジニアのHodaさんのポートフォリオサイトは、奇をてらったデザインではありませんが情報が非常にシンプルで分かりやすいと評判です。にもあるように、サイトの目的(何を見せたいか)や制作物、自分のスキルなどが一ページにスッキリまとめられており、採用担当者が知りたいことをすぐ見つけられます。配色も白背景に落ち着いたトーンで統一され、過度な装飾もなし。それでいて各プロジェクトの説明は箇条書きで読みやすく、「自分がどんな技術を使えて何が作れるのか」が一目瞭然です。ポイントは、凝ったデザインにしなくても内容勝負で十分アピールできるということ。自信のない方はまずこのようにシンプル路線で作り、後から装飾を加えていく形でも全く問題ありません。質実剛健な構成はそれだけで信頼感があります。
遊び心満載!空港風デザインの HISAMI KURITA さんのポートフォリオ
フロントエンドエンジニアのHISAMI KURITAさんのポートフォリオサイトは、一度見たら忘れない個性的なデザインです。まるで旅行前の空港にいるようなワクワク感が演出されており、ページをスクロールするとこれまでの実績が流れるように表示されていきます。まさに作品の中を冒険しているような感覚で、閲覧体験自体が楽しいのです。さらに所々に遊び心あるアニメーションがちりばめられていて、「こんな細部まで凝るなんて、この人は本当にモノづくりが好きなんだなあ」と伝わってきます。結果として、HISAMIさんのエンジニアとしてのこだわりや情熱がダイレクトに感じられるポートフォリオになっています。「見る人にインパクトを与えたい!自分の世界観を表現したい!」という方は、ここまで徹底してデザインコンセプトを作り込むのも一つの方法です。ただし凝ったサイトほど見づらくなりがちなので、HISAMIさんのように体験として楽しませつつ情報もちゃんと伝えるバランスは意識しましょう。
他にも「履歴書をゲーム風にしたポートフォリオ」や「コマンドライン風の入力で閲覧するポートフォリオサイト」など、世の中にはアイデア次第で様々なポートフォリオがあります。ここで紹介した例の共通点は、「自分の強みや個性を最大限引き出す工夫」をしていることです。シンプルであれリッチであれ、「この人ならでは」が感じられるものは採用担当者の記憶に残ります。「こうしなければいけない」という決まりはありませんので、ぜひ色々な先輩エンジニアのポートフォリオを参考にしつつ、あなたの魅力が伝わるオリジナル作品を生み出してくださいね。
初心者に嬉しい学習&転職サポート:「ポテパンキャンプU29」のススメ
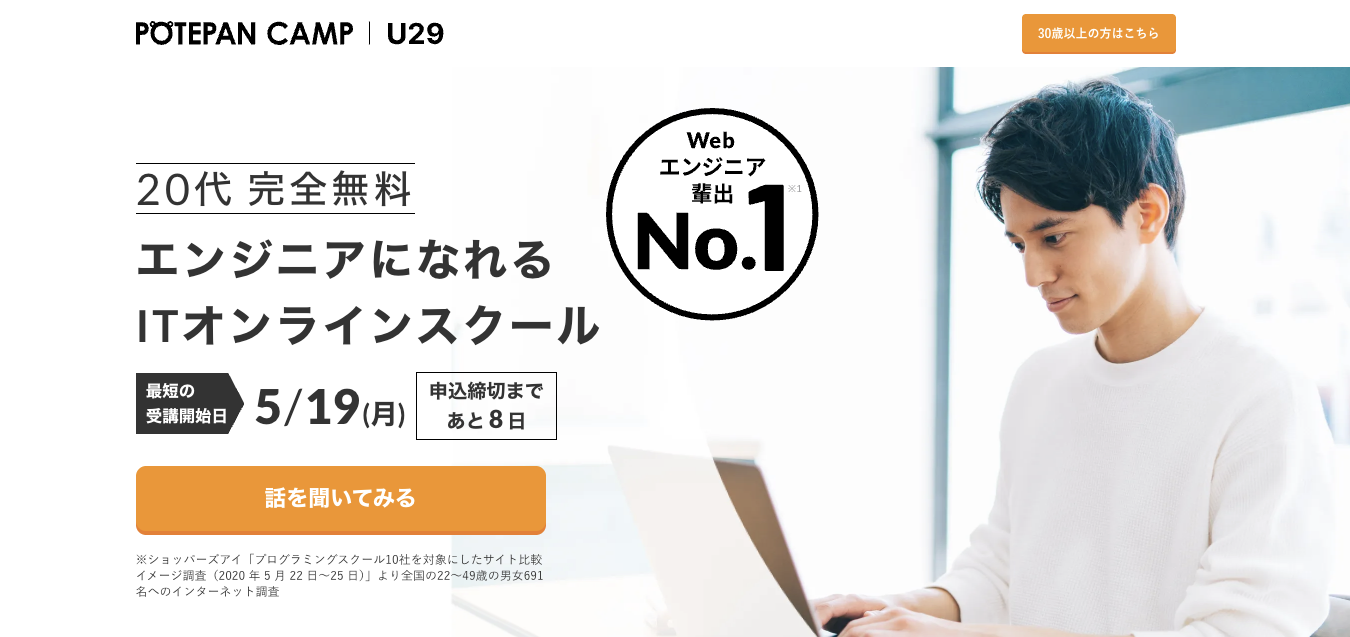
ここまでポートフォリオの重要性や作り方を見てきましたが、「それでもやっぱり一人で作るのは不安…」「もっと体系的に学びたい!」という方もいるでしょう。そんな駆け出しエンジニアの強い味方として最後に紹介したいのが、「ポテパンキャンプU29」というサービスです🚀
ポテパンキャンプU29は、その名の通り29歳以下限定で受講できる完全無料のプログラミングスクールです。オンラインで3ヶ月間、最新のWeb開発スキルを学び、卒業後はポテパンキャンプ提携のIT企業への転職を目指す実践的なコースになっています。カリキュラムはRuby on Railsを中心としたWeb開発の基礎から応用まで。未経験からでも挫折しないよう、質問サポートや受講生同士の交流コミュニティ、定期的な勉強会なども充実しており、一人で独学するより圧倒的に効率よくスキルを習得できます。
ポテパンキャンプの凄いところは、学習サポートだけでなく転職支援までフルで面倒を見てくれることです。実際の受講生からも「履歴書や職務経歴書の添削、面接練習、魅力的な企業の紹介、面接後のフォローまでサポートしてもらえた!」という声が上がっています。つまり、プログラミングを教えて終わりではなく、エンジニアとして就職が決まるまで伴走してくれるのです。特にU29コースは完全無料※なので、金銭的なハードルもありません。(※ただし転職意欲のある20代の方が対象で、首都圏の企業への就職を前提としています。)
ポートフォリオ作成に関しても心強いメリットがあります。カリキュラムの中で模擬プロジェクト開発やポートフォリオ制作が組み込まれているため、在学中に講師のアドバイスを受けながら自分のポートフォリオを仕上げることができます。何を作ればいいか迷っている初心者でも、課題を通じて一つプロジェクトを完成させられるので、卒業時には胸を張って見せられるポートフォリオ作品が手元に残るわけです。さらに転職活動では、その作品について深掘りして質問されることも多いですが、スクールでの学習内容を踏まえているので自信を持って答えられるでしょう。
ポテパンキャンプは実績も豊富で、受講生満足度95%・転職サポート満足度100%といった高い評価を誇っています。Webエンジニア輩出数No.1との呼び声もあり、未経験からエンジニア転職を成功させたい20代にとって最適な環境の一つです。公式サイトによると次回のU29コース開講日は近々とのことなので、興味のある方はチェックしてみてください。(人気ゆえ募集枠がすぐ埋まることもあるようなのでお早めに!)
まとめると、「ポートフォリオを作りたいけど何から始めれば…」という方は、思い切ってこうした無料スクールの力を借りるのも賢い選択です。独学では得られない体系的な指導や仲間との刺激があり、何よりプロに教わりながらポートフォリオを完成できるのは大きな安心感ですよね。ポートフォリオ作りは一人でもできますが、誰かにサポートしてもらった方が圧倒的に近道です。ぜひ選択肢の一つとして検討してみてください!
おわりに:あなたの物語をポートフォリオで語ろう
長文お付き合いいただきありがとうございます!今回は「ポートフォリオサイトのデザイン」について内容を詰め込んでみましたが、いかがでしたでしょうか?
ポートフォリオ作りは、最初はハードルが高く感じるかもしれません。しかし、考えてみれば自分のこれまでの歩みを物語としてまとめる作業でもあります。つまずいたこと、頑張って作ったもの、これからの夢——それらを一つの形にするのは、とてもエモい作業でもあります。完成したポートフォリオを眺めれば、「自分もここまで成長したんだな」ときっと自信が湧いてくるはずです。
この記事で紹介した基本原則やツール、事例やサービスをフル活用して、ぜひあなただけのポートフォリオを作り上げてください。最初は小さくていいんです。改善と追加を繰り返して育てていけばOK。ポートフォリオはまさにエンジニア人生の成長アルバム。これからページを増やしていくのはあなた自身です。
最後に:ポートフォリオはあなたの夢への切符。デザインやテクニックも大事ですが、一番大切なのはあなたの情熱です。画面の向こうの採用担当者に向けて、「自分はこんなにものづくりが好きなんだ!」という想いを込めてみてください。きっとその熱量は伝わります。
さあ、一歩踏み出してみましょう。あなたのポートフォリオが未来への扉を開いてくれることを、心から応援しています!🚀✨
(※本記事で紹介した「ポテパンキャンプU29」は20代限定・無料のエンジニアスクールです。詳しくは公式サイトをご覧ください。)